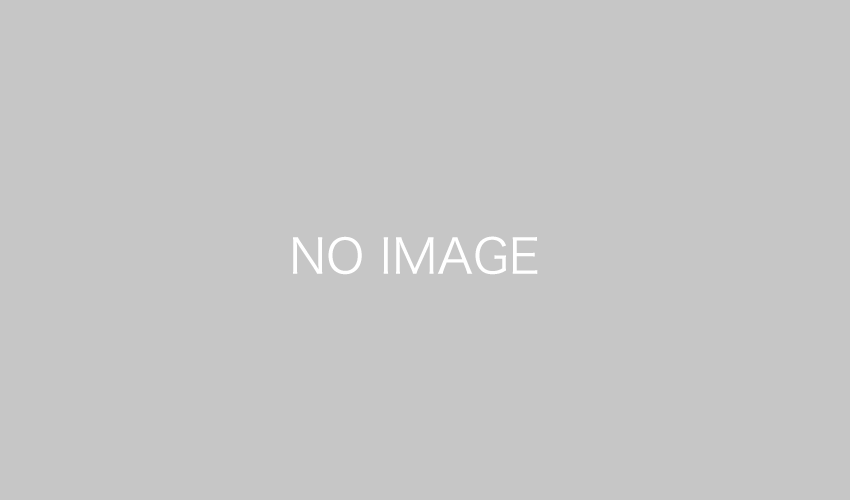ハラスメント調査の事実認定とは何か|認定基準と被害者供述の評価方法

なぜ「被害者の訴え=事実」と即断してはいけないのか
ハラスメント調査の目的は「事実認定」である
この記事のタイトルは、やや際どい表現だと感じられるかもしれません。
一歩間違えれば、「被害者を軽視しているのではないか」と受け取られる可能性もあります。
はじめに明確にお伝えしますが、被害者を軽視する意図は一切ありません。
では、なぜこのようなテーマで記事を書こうとしているのか。
それは、ハラスメントなどの事案において、会社として説明可能な判断を行うためには、感情に左右されない事実認定が不可欠だからです。
ハラスメント調査の目的は何でしょうか。
加害者を責めることでしょうか。
被害者の話をひたすら聞くことでしょうか。
いずれも重要ではありますが、完全な正解ではありません。
ハラスメント調査の目的は、事実関係を明らかにし、会社として責任ある判断を行うことです。
つまり、調査の本質は事実認定にあります。
なぜ事実認定が必要なのか。
それは、懲戒、配置、指導などについて、後から「なぜその判断をしたのか」を説明できる判断を会社として残す必要があるからです。
初動対応と事実認定を混同すると起きる問題
私は、被害者の訴えを信用してはいけないと言っているわけではありません。
即断してはいけないと言っているのです。
ここで言う即断とは、十分な検証や証拠収集を行わないまま、被害者と加害者を先に決めてしまうことを指します。
初動の段階、つまり証拠が十分に揃っていない状況で事実認定を行ってしまうと、その判断は管理職個人の印象や先入観が、そのまま会社の判断になってしまう危険性をはらみます。
普段の人柄、社内での評価、過去のトラブル歴など、無意識のうちに感情や偏見が入り込むからです。
感情が判断理由として残ってしまえば、会社として冷静で合理的な判断を下すことはできません。
初動設計の全体像については、
親記事「ハラスメント発覚後の初動対応|判断と事実認定の原則」で整理しています。
被害者の訴えは、まず何として扱うべきか
調査開始時点では「事実」ではなく「申告内容」である
警察ドラマやニュースなどで、「被害届」という言葉を耳にしたことがある方も多いと思います。
被害届は、受理された段階では、捜査を開始するための端緒、つまりきっかけとして扱われます。
最初から最後まで、絶対的な事実として扱われ続けるわけではありません。
私は、被害者からの申告も、これと同じ位置づけで捉えるべきだと考えています。
つまり、申告は調査を開始するための出発点であり、結論ではないということです。
被害者の申告によって、会社として調査が始まるのです。
申告を尊重することと、事実と認定することは別
被害者からの申告は、当然に尊重されるべきです。
申告に至るまでの経緯や、声を上げる勇気を考えれば、なおさらです。
しかし、申告を尊重することと、人事や懲戒の判断に使える事実として認定することは別です。
この二つを切り分ける作業において、感情が判断を曇らせる場面は少なくありません。
「○○さんなら、やっていそうだ」
「△△さんが、そんなことをするはずがない」
ハラスメントに限らず、職場でこのような言葉が交わされることは珍しくないのではないでしょうか。
ハラスメント調査における「供述評価」という考え方
供述はそのまま事実になるわけではない
供述は、管理職や調査担当者が判断するための材料の一つにすぎません。
供述そのものが結論になるわけではありません。
例えば、「LINEで執拗にデートに誘われた」という供述があれば、任意でLINEの内容を確認することで、事実関係を特定できる可能性があります。
供述は、事実認定に向けた入口に過ぎないのです。
評価の対象は「内容」だけでなく「全体の整合性」
とはいえ、供述だけでは事実認定ができないのかと言えば、必ずしもそうではありません。
複数人からの供述があり、それぞれの内容に整合性が認められる場合には、供述のみで事実認定が可能となるケースもあります。
重要なのは、一つ一つの発言の強さではなく、全体として矛盾がないかという視点です。
供述評価の基本① 一貫性を見る
時系列・場所・前後関係に矛盾はないか
同一人物から再度供述を確認する場合、あるいは複数人から供述を得る場合でも、時系列、場所、前後関係の整合性を確認することが欠かせません。
ハラスメント事案では、一方当事者の供述だけで完結することはほとんどありません。
必ず双方の供述を確認し、全体を整合させる必要があります。
表現の揺れと重要な矛盾を区別する
供述を確認する際に注意すべき点は、記憶の曖昧さによる表現の揺れなのか、意図的な言い逃れや矛盾なのかを見極めることです。
表現が変わったからといって、直ちに信用性が否定されるわけではありません。
供述評価の基本② 具体性と客観性を見る
抽象的な感情表現と行為事実を切り分ける
供述から証拠を見つけ、事実認定につなげるためには、具体性が重要です。
これは採用面接でも同様で、実際に経験した業務であれば具体的に説明できますが、経験していないことは抽象的な表現になりがちです。
供述に具体的な行為事実が含まれているかどうかが、重要な判断材料となります。
他の証拠と照合できる要素があるか
供述から証拠を収集できるか、他の供述と矛盾していないか。
この視点が重要です。
証拠がなくても、複数の供述に整合性が認められる場合には、信ぴょう性が高いと判断できることもあります。
利害関係がある=虚偽とは限らない
評価や処遇に不安を抱えている従業員の供述だからといって、信用できないと判断すべきではありません。
重要なのは、感情や先入観を排し、同じ基準で評価することです。
「信用できる供述」と「事実として認定できること」は違う
一部のみを事実として認定する判断
よくある勘違いとして、「全部認めるか、全部否定するか」という二択で考えてしまうケースがあります。
そのような判断をする必要はありません。
供述の一部のみを事実として認定することも、実務上は十分にあり得ます。
白黒がつかない場合の整理の仕方
証拠に乏しく、判断できない場合には、無理な事実認定は避けるべきです。
無理な認定は、短期的には楽であっても、後から管理職自身や会社に大きな負担として返ってきます。
ただし、調査を尽くしたこと、認定できなかった理由を、当事者双方に丁寧に説明する必要があります。
説明を行うことで、再発防止や抑止効果も期待できます。
まとめ:判断を誤らないために調査担当者が意識すべきこと
被害者配慮と事実認定は両立できる
被害者に配慮した冷静な判断は、被害者を切り捨てる判断ではありません。
むしろ、被害者からの信頼を得ることにつながります。
初動段階での整理が、最終判断を左右する
初動段階で事実認定は行わないものの、認定に向けた基礎資料の収集は欠かせません。
それが結果的には、被害者を守り、会社を守り、管理職自身を守る判断につながるということを、忘れてはならないのです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。
実務レベルでの初動設計が必要な場合は、
「危機対応・初動対応アドバイザリー」をご覧ください。